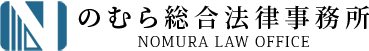1 はじめに
破産者(自然人)と親族が返済期限を定めずに金銭消費貸借契約を交わし(民法587条、同412条3項)、破産者が受任通知後に親族に対してだけ履行期前に返済をしたとします。この返済行為は、「債務の消滅に関する行為」であり、かつ「時期が債務者の義務に属しないもの」に該当します。そこで、当該返済行為が不当な偏頗行為(破産法252条1項3号)に当たり、免責不許可事由が存在することになるかが問題となります。
2 主観的要件について
まず、破産者の返済行為が「当該債権者に特別の利益を与える目的」があったかが問題となります。「特別の利益」とは、他の債権者と公平性を害する偏頗な利益であり、かつ「特別の」と評価されるだけの利益を意味します。また、債務者において、単なる認識では足りず、積極的な目的行為性が認められる必要があります(条解破産法1718頁)。
また、破産者の返済行為が「他の債権者を害する目的」があるかも問題となります。「他の債権者を害する目的」とは、債権者を害することを主たる目的とすることまでは必要ないが、債権者の破産手続における満足を積極的に低下させようとする害意が存在することが必要となります(条解破産法1718頁、同1714頁)。
以上、破産者の返済行為が、「当該債権者に特別の利益を与える目的」があり、かつ「他の債権者を害する目的」があると認められれば、不当な偏頗行為(破産法252条1項3号)に当たり、免責不許可事由が存在することになります。