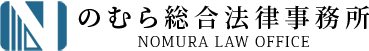1 はじめに
甲が乙と養子縁組をし、その後、乙が丙と養子縁組をしたとします。
この場合、乙が甲よりも先に亡くなった場合、丙は、甲の推定代襲相続人となります。
乙の死後、甲と丙との関係が良好な場合は問題がありませんが、不仲となった場合、甲は、丙の代襲相続人としての地位をはく奪したいと考えたとします。この場合、廃除の申立て(民法893条)をするか、死後離縁の申立て(民法811条6項)を行うことになります。
以下では、甲が死後離縁の申立てを選択したのに対し、原審が廃除制度の潜脱であるとして申立てを却下しましたが、高裁はそれを覆した事例(大阪高裁令和3年3月30日決定)を紹介します。
【関連記事】
✔廃除についての解説記事はこちら▶コラム:推定相続人の廃除
2 裁判例
1 事案の概要
甲会社を共同経営していたAとBの間には、長女C、次女Dがいた(男子がいなかった)。
CはEと婚姻し、EがA、Bと養親縁組した。
Eは、養子縁組後、甲会社の代表取締役に就任し、経営をしていた。
CとEとの間には子がいなかったので、将来の後継ぎのため、Eは、次女Dの三男Fと養子縁組をした。
Eは、Aに先立ち亡くなった。Fは子としてEの多額の遺産を相続した。
Fは、代表取締役に就任し、甲会社を経営するようになった。
Bは、Aに先立ち亡くなった。Fは代襲相続人としてBの遺産を相続した。
AらとFとの間で、甲会社の経営方針が合わなくなった。そのため、Fは、甲会社は代表取締役・取締役の地位を辞することになった。
Aは、自身の推定代襲相続人であるFに相続させたくたいとの意向に基づき、AとEとの養子縁組を解消するため、死後離縁の申立てを家庭裁判所に行った。
2 原審
原審は、「本件申立ては、推定相続人廃除の手続によらずに利害関係参加人から推定代襲相続人の地位を失わしめる目的、すなわち推定相続人廃除の手続を潜脱する目的でなされた恣意的なものであると認めざるをえないから、これを許可するのは不相当である。」とし、死後離縁の申立てを却下しました。
3 抗告審
抗告審は、まず、死後離縁が認められるための要件について次のとおり一般論を示しました。
「養子縁組は、養親と養子の個人的関係を中核とするものであることなどからすれば、家庭裁判所は、死後離縁の申立てが生存養親又は養子の真意に基づくものである限り、原則としてこれを許可すべきであるが、離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなど、当該申立てについて社会通念上容認し得ない事情がある場合には、これを許可すべきではないと解される。」
その上で、以下のとおり、養親に廃除の意思が認められるとしても、死後離縁の申立てを許可されるとしました。
「そして、利害関係参加人は、亡Iの死亡により、抗告人の代襲相続人の地位を取得したものではあるが、既に、大学を卒業して就労実績もある上、亡I及び亡Eから相当多額の遺産を相続しているものであって、上記代襲相続人の地位を喪失することとなったとしても、生活に困窮するなどの事情はおよそ認められない。その上、抗告人と利害関係参加人との関係は著しく悪化しており、利害関係参加人は、Hの代表取締役及び取締役を辞任したことも認められる。
上記の諸事情に照らせば、本件申立てを許可することにより、利害関係参加人が抗告人の代襲相続人の地位を失うこととなることを踏まえても、本件申立てについて、社会通念上容認し得ない事情があるということはできない。」