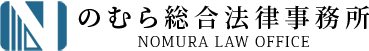1 はじめに
婚姻費用分担調停(審判)で婚姻費用の金額が定まったが、その後の事情変更により調停(審判)で定まった金額を支払うことができなくなった場合、当該義務者は家庭裁判所に対し婚姻費用減額調停を申し立てることができます。
以下では、義務者が前件審判後に婚姻費用減額調停を申し立てたが不成立となり、審判で減額されたものの、抗告審は原審とは異なり減額を認めなかった事例(大阪高等裁判所令和2年2月20日決定、家庭の法と裁判31号64頁)を紹介します。
2 裁判所の判断
原審は、義務者が提出した診断書の記載内容の信用性を吟味することはありませんでした。これに対し、抗告審は、診断書の記載内容、その作成時期を細かく検討するだけでなく、義務者が自主退職した時期、就職活動の状況などを考慮し、義務者には現在も前件の審判成立時と同じ稼働能力があると判断しました。
「(1)・・抗告人は、同年9月1日及び同年10月4日にD医師に診断書の作成を依頼し、抑うつ状態のため休業加療が必要である旨記載された診断書の交付を受けたが、いずれの診断書も、具体的な症状が全く記載されていないし、抗告人の主訴に基づいて作成されたと推認されるから、これらをもって直ちに抗告人が実際に休業加療を要する状態にあったと認めることはできない。現に、抗告人は、同年9月1日以降も休業することなく勤務を継続していたのである。
(2)ところが、抗告人は、平成30年10月20日、13年間も勤務していたHを自主退職し、同月30日、婚姻費用分担金の減額を求めて本件調停申立てをした。しかし、抗告人の同年1月1日から同年10月20日までの給与収入は363万5000円であり、これを年額に換算すると、約453万円(363万5000円÷293日×365日)となり、前件審判において婚姻費用分担金算定の基礎とされた給与収入462万5000円をわずかに下回るだけである。
(3)抗告人は本件調停申立て後、平成30年11月16日に受診した以後は約5か月間受診しなかったが、本件調停が平成31年3月25日に不成立となり、本件審判手続に移行した約半月後の同年4月10日にD医師の診察を受け、令和元年5月7日、D医師に診断書の作成を依頼し、気分変調症(慢性の抑うつ状態)であり、うつ状態の持続から一般就労は困難な状態である旨記載された診断書の交付を受けた。しかし、上記診断書も、前同様に具体的症状は全く記載されておらず、どの程度就労が制限され、どのような形態であれば就労可能であるのか明らかではない。このような上記診断書の作成時期、経緯及び記載内容からすれば、抗告人は、本件審判手続において自己に有利な資料として提出するために上記診断書の交付を受けた疑いなしとしない。したがって、上記診断書をもって抗告人が抑うつ状態のため定職に就いて継続的に勤務することが困難な状態にあると認めることはできない。
(4)しかも、抗告人は、Hを自主退職後、散発的ではあるものの、I、J及びEに勤務して給与収入を得る傍ら、平成31年春ころには第一種衛生管理者の免許等を取得し、令和元年秋ころにはF大学G学部(通信教育課程)の入学試験に合格し、令和2年4月に入学する予定である。このように、抗告人は、自己の将来に役立てるために免許等の取得や大学入学を目指して意欲的に取り組み、実現しているのであるから、就労困難であるほどの抑うつ状態であるというのは不自然であり、信用することはできない。抗告人が就労困難でないことは、抗告人が令和元年8月以降は受診も服薬もしていない上、同年9月11日の原審第4回審判期日において、相手方との審判等がなければ、身体、精神上特段の問題はない旨陳述していることからもうかがえるところである。
(5)以上のとおり、抗告人は、前件審判後、断続的にD医師の診察を受け、Hを退職してほとんど収入がない状態となっているが、自らの意思で退職した上、退職直前の給与収入は前件審判当時と大差はなかったし、退職後の行動をみても、抑うつ状態のため就労困難であるとは認められないから、抗告人の稼働能力が前件審判当時と比べて大幅に低下していると認めることはできず、抗告人は、退職後現在に至るまで前件審判当時と同程度の収入を得る稼働能力を有しているとみるべきである。したがって、抗告人の精神状態や退職による収入の減少は、前件審判で定められた婚姻費用分担金を減額すべき事情の変更ということはできず、抗告人の本件申立ては理由がない。」
3 最後に
以上、婚姻費用減額の裁判例について説明しました。お困りの方は、のむら総合法律事務所までご相談ください。
✔のむら総合法律事務所に関するご案内はこちら▶事務所紹介