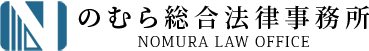1 はじめに
被相続人の遺産の中に積極財産だけでなく消極財産が含まれていた場合、遺留分算定の基礎財産の算出においては消極財産を控除し(民法1043条1項)、遺留分侵害額の算出においては加算することになります(民法1046条2項3号)。以下では、具体例を用いて説明していきます。
2 具体例
被相続人は、令和6年1月に亡くなったところ、遺産である預貯金2000万円を相続人以外の甲に対し遺贈する旨の遺言を作成していました。また、被相続人は、亡くなる5年前、相続人である子の乙に対し生計の資本として1億8000万円の生前贈与をしていました。さらに、被相続人は、銀行に対し1000万円の負債がありました。もう一人の相続人である子の丙は、誰に対し、いくらの遺留分侵害額請求をすることができるでしょうか。
3 計算
1 遺留分算定の基礎財産
遺贈された預貯金2000万円は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に該当するため、基礎財産に含まれます(民法1043条1項)。
また、「贈与した財産の価額」も基礎財産に含まれることになります(民法1043条1項)。具体的には、亡くなった日から遡って10年以内に相続人に対してなされた特別受益としての生前贈与も基礎財産に含まれることになります(民法1044条3項)。本件では、相続人である乙に対しなされた特別受益に該当する生前贈与1億8000万円分は、亡くなる5年前になされているので、基礎財産に含まれることになります。
さらに、基礎財産からは「債務の全額を控除」することになります(民法1043条1項)。本件では、被相続人の債務として1000万円ありますので、この金額を控除することになります。
以上を整理すると、基礎財産は、2000万円+1億8000万円-1000万円=1億9000万円となります。
2 甲の遺留分額
1億9000万円×2分の1×2分の1=4750万円となります(民法1042条1項)。
3 甲の遺留分侵害額
甲の遺留分から甲の取得分を控除し(民法1046条2項1号2号)、甲の「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務・・の額」を加算することになります(同項3号)。
まず、甲の遺留分額から控除するものはありません。次に、被相続人の債務は1000万円で、甲の法定相続分は2分の1なので、甲が承継する債務の額は1000万円×2分の1=500万円となります。そのため、遺留分額に500万円を加算することになります。
以上を整理すると、甲の遺留分侵害額は、4750万円-0円+500万円=5250万円となります。
4 請求相手
本件では、受遺者である甲、受贈者である乙がいます。このように「受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する」ことになります(民法1047条1項1号)。
したがって、まず、丙は、受遺者である甲に対し、2000万円の遺留分侵害額請求をすることになります。その後、受贈者である乙に対し、残り3250万円の遺留分侵害額請求をすることになります。
4 特定財産承継遺言の場合
1 はじめに
2の事例について、「乙に全ての遺産を相続させる」という特定財産承継遺言だった場合はどうなるでしょうか。
2 計算
遺留分算定の基礎財産、丙の遺留分額は変わりませんが、丙の遺留分侵害額は変わってきます。
というのも、「乙に全ての遺産を相続させる」という遺言には相続分の指定も含まれていると解することができるため(民法902条1項)、丙の(指定)相続分が0%、乙の(指定)相続分が100%となります。そうすると、債務1000万円については、乙が100%相続することになり、反対に丙は一切相続することはありません(丙の続分は0%)。
つまり、丙の「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務・・の額」(民法1046条2項3号)は、1000万円×0%=0円となります。
以上を整理しますと、丙の遺留分侵害額は、4750万円-0円+0円=4750万円となります。
よって、丙は、乙に対し、4750万円の遺留分侵害額請求をすることになります。
5 最後に
遺留分について一般的なことは関連記事をご参照ください。
【関連記事】
✔遺留分一般についての解説記事はこちら▶遺留分