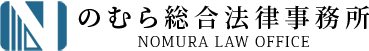1 はじめに
財産分与が争点となった最近の裁判例である大阪高裁令和3年8月27日(家庭の法と裁判36号)をご紹介します。
2 事案の概要
夫婦ともに医師で、妻が夫と別居したのは平成28年8月15日でした。別居時の妻名義の口座の預貯金の合計が300万円に満たない額しか存在しませんでした。もっとも、妻は平成24年頃から別居までの間の4年間の間に合計3386万円の収入を得ていました。そこで、夫側が、妻は離婚に備えて自己名義の多額の資産を隠匿していたとし、原審において、平成28年8月15日から遡って10年間の金融機関口座の取引履歴についての調査嘱託、文書提出命令の申立てをしました。しかし、原審は、いずれも却下した上で、妻に隠し財産があるとは認められないと判断しました。
3 判旨
1 一般論
「裁判所は、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」ことになるが(民法768条3項)、その判断において考慮すべき事情としては、「当事者双方がその協力によって得た財産の額」及び財産形成に対する寄与の程度が清算的財産分与の額の判断において重要な考慮事情となるほか、それ以外の事情についても、当該事情を考慮することが財産分与における当事者の衡平を図るうえで必要かつ合理的であると認められる場合には、これを前記「一切の事情」として考慮し、裁判所の合理的な裁量に基づいて、「財産分与の額及び方法を定める」ことになる。」
2 あてはめ
「平成24年から平成27年までの給与収入については、それだけでも合計約3386万円にも上る高額な所得であり(これに加えて、平成28年においても、基準時までに相当の給与収入があったと認められる。)、以上の所得は基準時の約4年前から得ていた収入であって、このうちの一定額が税金や社会保険料の支払のほか、個人的な生活費や職業費、子らの教育費などに充てられていたとしても、その全額が基準時までに、被控訴人によって費消されたものであるとは考え難い。そして、被控訴人が主張するとおり、被控訴人において、平成24年以降も自己が負担すべき租税公課及び社会保険料や個人的な生活費や職業費等の支払を自らの給与収入から負担していた事実を認めることができるとしても、被控訴人は、これらの支出について、毎年、どれだけの額の支出をしたのかについては具体的に明らかにしておらず、別居前の支出についての的確な証拠も提出していない。そして、以上に認定した被控訴人の平成24年から別居時までの給与収入額のほか、基準時における被控訴人名義の預貯金残高の合計が300万円にも満たない額(前記認定の特有財産部分を除く。)であったことに加え、被控訴人の別居後の支出が多くとも年間約850万円程度であり(乙6等)、別居以前は、別居後とは異なって、住居費(水道光熱費を含む。)や食費、教育費等の家計支出の多くを控訴人の収入から支払っていたことなど、控訴人及び被控訴人の当時の家計財産の管理状況及び家計に対する負担状況に照らせば、被控訴人は、平成24年から別居までの間、その間に得た給与収入の二、三割程度の貯蓄を行うことができたものと認められる。」